みなさん、こんにちは!スタッフの近藤です。
今回はタイトルの通り、雪の結晶の「形」に注目してサイエンスとプログラミングを学んでいきます。それでは2月4日(土)と9日(木)の模様をお届けいたします!
サイエンス編
まず、前回習ったことの復習をしました。「氷晶って何角形?」から始まって、氷晶が成長して「雪の結晶」になる過程を学んでいきます。
雪そら第二回のキーワードは「形」です。
雪の結晶にはいろいろな形があることをみんなで観察しました。

綺麗〜!おもしろい形〜!という感想だけで終わらないのがラッコラです。
さて、結晶の角の数はいくつあるでしょうか。氷晶が基本の形(六角形)を元にして、大きくなっている証拠ですね。そんなことを確認しながら、自分のお気に入りの雪の結晶を選んで、スケッチしてもらいます。


子供たちの手元を見てください、何やらトレーシングペーパーが結晶に比べて小さいですね。
雪の結晶は六角形なので、6分の1を描いてしまえば後はその「繰り返し」なんです。
この繰り返しは、今回のプログラミングでも大切なキーワードになっています。
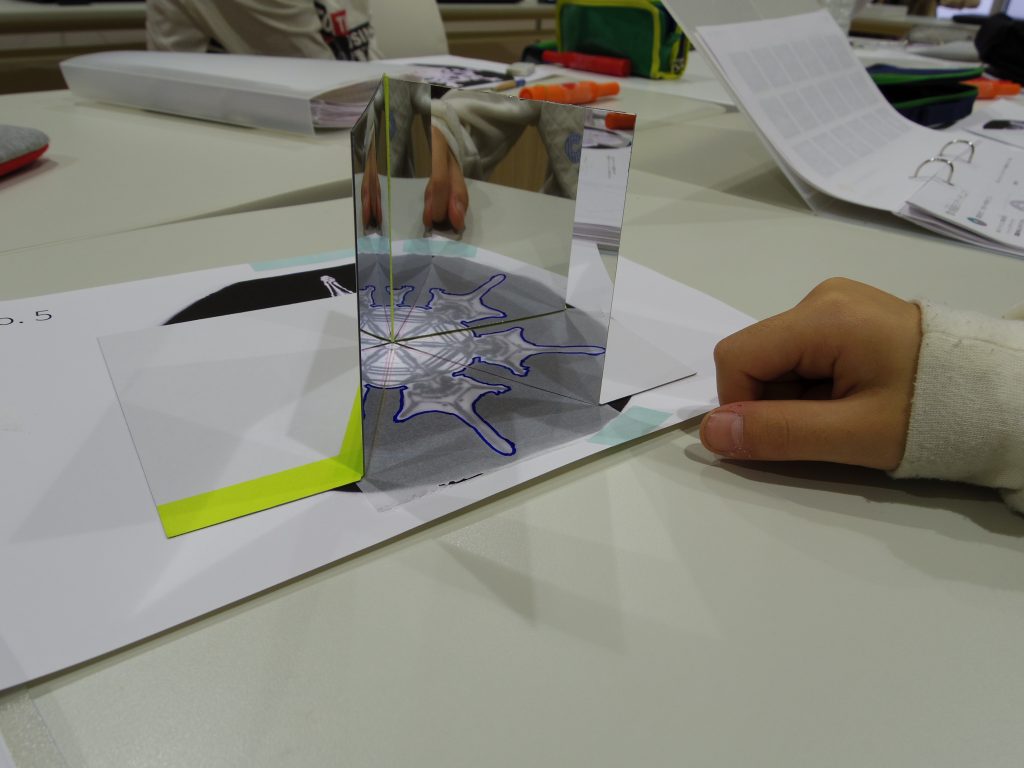
サイエンス編の最後には、メインタイトルである「ダイアグラム」のお話をしました。
雪の結晶に関するもので「小林のダイアグラム」というものがあります。
雲の中でどんな雪の結晶ができるのかは、水蒸気の量と気温によって決まることをまとめたものです。つまり、空から降ってくる雪の結晶をみると、雲の様子がわかってしまうんですよね。すごい!
プログラミング編
まずは、サイエンス編でスケッチした結晶を、マス目を使って簡単に描いてみます。
これが今日、プログラミングで描く結晶の設計図になります。
選んだ結晶がみんな違うので、もちろん難易度は人によって異なります。
その後は、いつものようにプログラミングの勉強です。
今回のポイントは、繰り返しを行う「for文」です。


今日の内容をお勉強したところで、いよいよパソコンに向かって結晶づくりのスタートです!
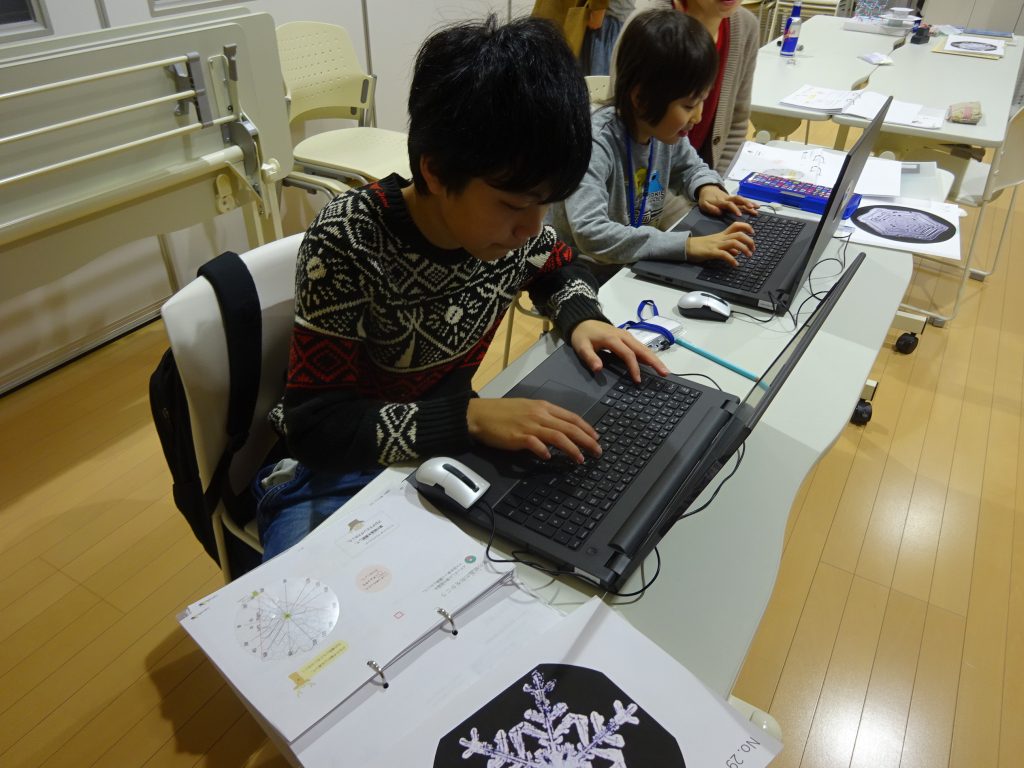
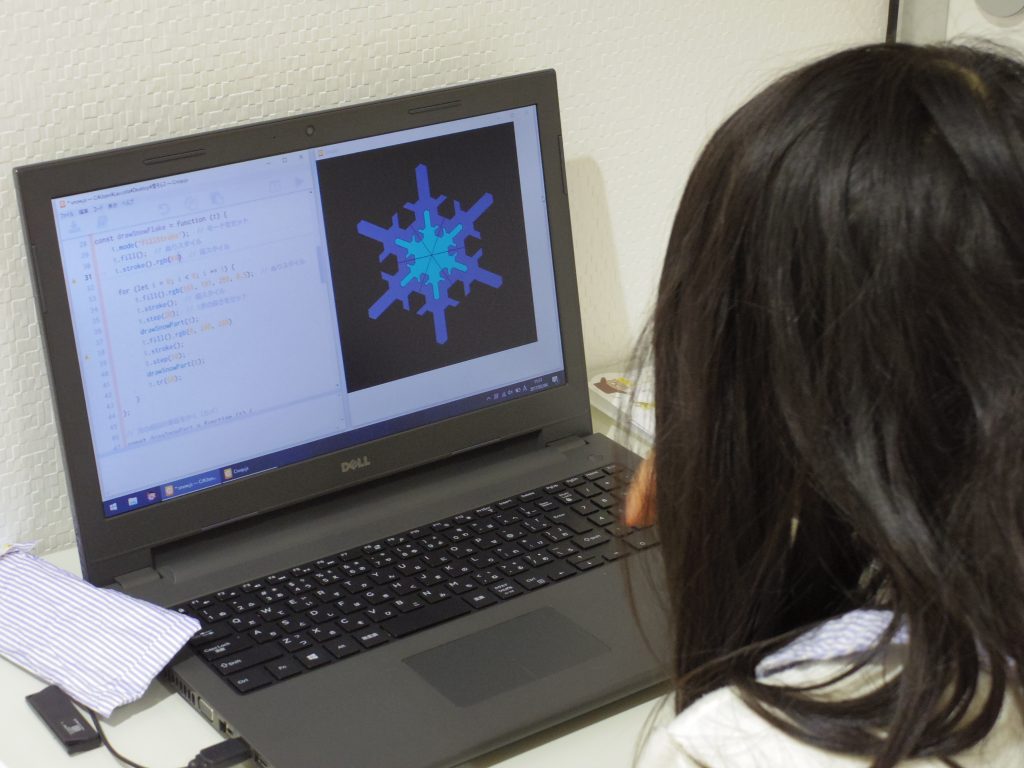
最後に今日やったことをワークシートにまとめて、第2回は終わりです。
子供たちに書いてもらった感想を少しだけ紹介します。
◆サイエンス編の感想
「けっしょうの形がたくさんあっておもしろかった」
「つづみ状がよかった」
「ゆきのけっしょうが1cmになるとしりおどろきました。」
◆プログラミング編の感想
「じかんがかかったけど雪のけっ晶をつくるのが楽しかった」
「きれいにできたのでたのしかったです。」
「けっしょうの形を作るのがむずかしかった」
今回のプログラミングは、いつも以上に角度や距離を打ち込まなければならず、子供たちにとっては大変な作業でした。でもみんな最後まで諦めず、素敵な結晶を作り上げていました!
次回はその結晶が……雪そらコース第3回をお楽しみに!

